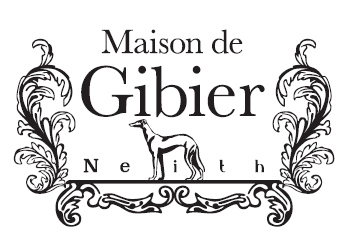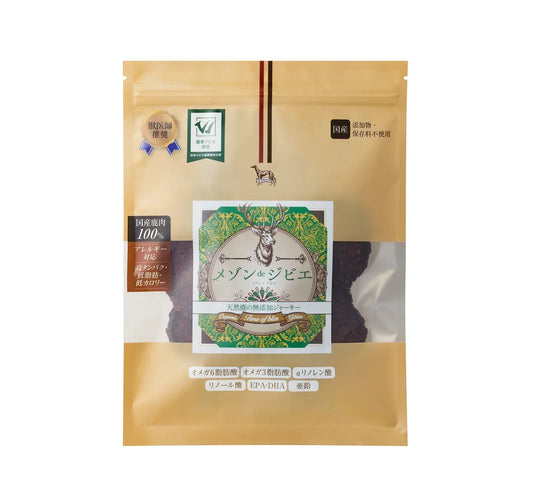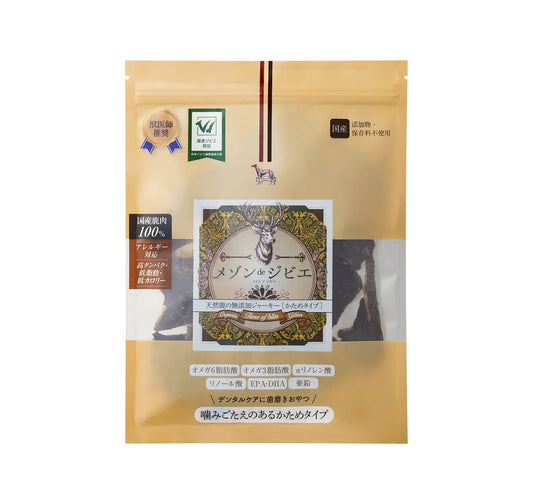「最近、愛犬の皮膚が赤い気がする」「お腹をこわしやすくなったかも」そんな小さな異変の原因は、実は“食べ物”が関係しているかもしれません。
犬の食物アレルギーは、皮膚炎・下痢・嘔吐・涙やけなど、いろいろな形で現れます。
しかしその多くは、「体質だから」「季節性のものかも」と見過ごされがちです。
とくに鶏肉や小麦など、日常的に与えている食材が原因のこともあるため、食事の見直しが大きな鍵になります。
本記事では、犬の食物アレルギー対策として今選ぶべきドッグフードや「犬のアレルギー症状の見分け方」「ドッグフードの成分チェックポイント」などについて詳しく解説しています。
なぜ今、犬の食物アレルギー対策が注目されているのか?
その背景を理解するための5つのポイント
-
動物病院で「皮膚トラブル」「下痢」「嘔吐」などの相談が年々増加し、特に食物アレルギーの疑いが強いとされるケースが目立っている
-
市販のフードに含まれる小麦・鶏肉・添加物がアレルゲンとなりやすく、特に小型犬や室内飼育犬に慢性的な症状が見られることが多い
-
飼い主が自己判断でフードを変えても改善せず、正しい知識や情報源へのニーズが高まっている
-
SNSの普及により「愛犬も人と同じように健康管理が必要」という意識が広がり、フード選びも“医療的な視点”が重視されている
-
東京大学をはじめとする研究機関や獣医師の監修付き記事が増え、食事療法の重要性が社会的にも認知され始めている
愛犬のアレルギー症状に悩む飼い主の間で、「何を食べさせたらいいのか分からない」という声が増えています。
特に飼い犬の皮膚が赤くなったり、しきりに掻いていたり、下痢や嘔吐、涙やけが続いたりするような症状は、単なる体質ではなく“食べ物が原因かもしれない”と考える方が増えてきました。
犬の食物アレルギーとは、特定の食材に対して犬の免疫システムが“異物”と判断し、体の中で拒絶反応を起こしてしまう状態のことです。
特に鶏肉や小麦など、日常的に摂取している食材が引き金になることも多く、見落とされがちです。
こうした背景の中で、アレルゲンになりにくい“鹿肉”や“馬肉”といった新奇タンパク質を用いたフードが注目されています。
加えて、東京大学の研究チームが「人とペットの共通疾患」に着目した取り組みを進めており、専門的な視点からも食事によるアプローチの重要性が再認識されています。
この記事では、今なぜ犬のアレルギー対策が必要とされているのか、その背景と合わせて丁寧に解説していきます。
アレルギーの犬が増えている理由は?何が原因なのか?
|
分類 |
具体的な要因 |
補足・背景情報 |
|
体質の変化 |
遺伝的にアレルギー体質の犬が増加 |
特に小型犬・純血種に多く、皮膚疾患のリスクが高まっている |
|
飼育環境 |
室内飼育によるアレルゲンの蓄積 |
犬のフケや唾液由来のタンパク質が空気中に舞い、慢性的な刺激になる |
|
食事・栄養 |
小麦や鶏肉などアレルゲンとなりやすい食材の摂取 |
市販フードに含まれる添加物や穀物が原因となるケースも |
|
ストレス要因 |
運動不足や騒音など生活環境の変化 |
自律神経の乱れが免疫機能に影響し、皮膚や腸に不調が現れやすい |
|
診断技術の進歩 |
アレルギーの認知・診断が普及 |
飼い主の意識向上とともに、獣医師の診断件数も増加している |
(犬のアレルギー増加の要因)
犬のアレルギー性疾患が増えている背景には、単なる体質だけでなく「現代的な生活環境の変化」や「食事の影響」など、複合的な要因が存在します。
たとえば、昔に比べて犬が外で過ごす時間は減り、エアコンの効いた室内で過ごす時間が長くなりました。
これにより、ダニ・ホコリ・花粉といった室内アレルゲンが蓄積しやすくなり、皮膚や呼吸器のトラブルにつながりやすい状態になっています。
さらに近年では、遺伝的にアレルギー体質を持つ小型犬や純血種が人気で、実際に皮膚炎や涙やけ、慢性的な下痢などの相談が増加傾向にあります。
加えて、市販のドッグフードの中には小麦・鶏肉・人工添加物など、アレルゲンとなりやすい食材が含まれていることもあり、知らずに与え続けて症状が悪化するケースも少なくありません。
ある会社のアンケート調査によると、獣医師の約42.6%が「過去1年間で犬のアレルギー症状が増えた」と実感しており、ペット医療の現場でも「ペットのアレルギー」が深刻なテーマとなりつつあります。
出典:PRTIMESS「犬猫のアレルギー性症状が増加傾向、約4割の獣医師が定期検診を推奨。」
犬の食物アレルギー症状とは?チェックポイントを知ろう
|
症状カテゴリ |
主な症状 |
見分けるポイント |
|
皮膚症状 |
かゆみ、赤み、脱毛、フケ、湿疹 |
特に耳・口周り・足先・背中などに集中する傾向 |
|
消化器症状 |
嘔吐、下痢、軟便、食欲不振 |
食後30分以内または数日後に症状が出る場合もある |
|
目・鼻の症状 |
目の充血、涙やけ、くしゃみ、鼻水 |
季節性でなければ食事が原因の可能性あり |
|
行動変化 |
しきりに掻く、舐める、落ち着きがない |
慢性化すると夜間の睡眠妨害やイライラが目立つ |
|
その他 |
耳の悪臭、頻繁なおしり歩き、体臭の変化 |
症状が多部位に広がっている場合は要注意 |
(食物アレルギーに見られる代表的な症状一覧)
愛犬の様子が「最近なんとなく違う」と感じたことはありませんか?
特に皮膚のかゆみや脱毛、下痢や嘔吐といった症状が続いている場合、それは“ただの体調不良”ではなく、食物アレルギーのサインかもしれません。
犬のアレルギー症状は、人間以上に見た目だけでは判断が難しいものです。
アトピー性皮膚炎やノミアレルギーと混同しやすく、食後すぐに症状が出る「即時型」だけでなく、数日後に現れる「遅延型」もあるため、原因の特定には慎重な観察が必要です。
特に多いのは、耳や口元、足先、背中など「かゆみの出やすい部位」に集中する皮膚症状です。
このような症状が愛犬に繰り返されるようであれば、一度アレルギー検査や食事の見直しを検討してみる価値があります。
そして大切なのは、「今の食事が合っていない可能性がある」ことに早めに気づくことです。
「うちの子、食物アレルギーかも?」と思った時に飼い主がやるべきこと
|
チェック項目 |
具体的な観察ポイント |
|
症状が“繰り返される部位”があるか |
耳・口周り・足先・背中などにかゆみや赤みが出ていないか |
|
食事変更と症状のタイミングを振り返る |
新しいフードやおやつを与えた直後や数日後に症状が出ていないか |
|
毎日の食事内容と体調を記録する |
便の状態・回数・食事時間も含めて日記形式で残す |
|
除去食を単一タンパクで試す |
鹿肉・馬肉などの新奇タンパクを選び、1種類に限定して与える |
|
かかりつけ獣医と一緒に進める |
検査や食事療法の進め方は獣医師の指導のもと行うのが安心 |
(愛犬のアレルギーに対する飼い主の判断ポイント)
ちょっとした愛犬の違和感を覚えたとき、多くの飼い主さんは「とりあえず様子を見る」という判断をしがちです。
しかし、アレルギーは個体差が非常に大きく、原因もさまざまです。
食べ物だけでなく、環境・ノミ・ハウスダストなど多岐にわたるため、自己判断での様子見はかえって逆効果になることもあります。
特に食物アレルギーの場合、症状が皮膚炎や消化器不調といったよくある体調不良と重なりやすく、見落とされがちです。
だからこそ一見「軽い症状」であっても、頻繁にその症状を繰り返す場合は早めに動物病院で検査を受けることをおすすめします。
油断は厳禁!? 食物アレルギーが原因で愛犬が亡くなることもあります!
|
ポイント |
補足説明 |
|
犬にもアナフィラキシーショックは起こる |
食物アレルギーが原因で、命に関わる急性症状を引き起こすケースが報告されている |
|
“微量のアレルゲン”でも発症する可能性がある |
表記外の混入でもショックを起こす例が確認されており、極めて注意が必要 |
|
アレルゲンの混入が“表示されていない”ことがある |
療法食においても、意図せぬアレルゲンが混入していた事例が実在する |
|
人間と比べて“表示義務が緩い”のが現状 |
ペットフードに関する表示基準はヒト食品ほど厳しくない |
|
“早期発見”と“すぐの対応”が生死を分ける |
重篤化する前に気づいて病院へ。遅れは命取りになることもある |
(犬のアレルギーについて知っておくべき5つの重要ポイント)
「少し痒そうだな」「お腹を壊しやすいな」——そうした軽い愛犬の違和感も、実は食物アレルギーの初期サインかもしれません。
そして、覚えておいて欲しいのが犬にも「アナフィラキシーショック」という命に関わる急性アレルギー反応が生じることです。
特に注意が必要なのは、“表記されていないアレルゲン”の混入です。
実際、過去のフード検査では成分欄に記載されていなかった小麦や卵白が検出された事例があったそうです。
このような微量のアレルゲンの混入によって、犬が食後60分以内に呼吸困難・血圧低下を起こし、アナフィラキシーのような症状に至った可能性がある症例も指摘されています。
またペットフードは人間用食品と異なり、アレルゲン表示の義務がなく、製造ラインの分離や検査体制もメーカー任せになっているのが現状です。
こうした背景をふまえると、単に「無添加」「グルテンフリー」と書かれているだけで選ぶのは危険でしょう。
大切なのは、「どの基準で製造され、どのように管理されているか」まで確認すること。
そして何より重要なのは、少しでも異変を感じたらすぐに動物病院へ相談することです。
食物アレルギーは正しく対処すれば改善も予防もできますが、重篤化すれば数分単位で命に関わります。
「うちの子は大丈夫」と思い込まず、小さなサインを見逃さない。それが、飼い主ができる最大の予防策です。
ドッグフードが原因でアレルギーが発症することも!アレルゲンになりやすい要素と理由
|
分類 |
アレルゲンとなりやすい要素 |
代表例と補足 |
|
たんぱく源 |
アレルギーを引き起こしやすい動物性タンパク |
鶏肉、牛肉、乳製品は発症例が多い |
|
穀物類 |
小麦・トウモロコシなどのグルテン・でんぷん |
グルテン等に敏感な犬に影響する可能性あり |
|
添加物 |
保存料・着色料・香料などの人工成分 |
BHA・BHT・合成ビタミンEなどが疑われることも |
|
加工方法 |
高温処理・酸化した油脂の使用 |
タンパク質が変性し、アレルゲン性が高まることがある |
|
保存・保管 |
酸化・湿気・虫の混入など品質劣化 |
酸化した脂質が体内炎症を引き起こすリスクあり |
ドッグフードに含まれる成分が、実はアレルギー症状の原因になっているケースは少なくありません。
「高いフードなのに皮膚炎が治らない」「涙やけが続いている」――そんなときこそ、ドッグフードの中身の見直しが必要かもしれません。
実際に、日本国内の獣医師調査では犬のアレルギー相談のうち、約4割が「食事が原因かもしれない」と報告されています。
特に、鶏肉・牛肉・小麦・乳製品などはアレルゲンになりやすい主要食材です。これらは長年にわたって使われてきた分、犬の免疫が過敏に反応しやすくなる傾向があります。
さらに、2025年の調査データでは市販フードの約6割以上に人工保存料や香料が使用されており、免疫のバランスを崩す要因になることもあります。
加えて、高温加工によって変性したタンパク質は、本来は無害な成分であっても“異物”と認識され、体内で拒絶反応を起こす可能性が指摘されています。
また、開封後に空気に触れて酸化したフードは、消化不良や皮膚の炎症を引き起こすリスクがあり、特に小型犬やシニア犬での影響が顕著だとされています。
そして、実はあまり知られていませんが、ドックフードの中にはヒトの食品での表示基準を超える量のアレルゲンの混入が認められているケースがあることをご存知でしょうか?
実はアレルゲンが多かった!? ドッグフードの知られざる裏側
-
食物アレルギー用の療法食5製品中、3製品から小麦が検出された
→ 一部製品では20ppm以上と、ヒト用食品なら表示義務が生じるレベル -
原材料に記載のない“卵”が1製品から検出された
→ 卵白由来のタンパク質が11.2ppm含まれていた事例も -
“乳”はすべての製品で不検出だったが、1製品では微量(1.1ppm)を検出
→ 完全除去されているとは言い切れない点が課題 -
日本のドッグフードには“アレルゲン表示義務”が存在しない
→ ペットフード安全法でも、微量混入に関する規制はなし -
療法食であっても、製造過程での混入リスクが防ぎきれていない
→ 製造ライン共有・洗浄不足などの構造的問題が背景に
「このフードなら大丈夫」――。そう信じて買ったアレルギー対応の療法食に、実は“見えないアレルゲン”が含まれていたとしたら、あなたはどう感じるでしょうか?
2021年の国内調査では、原材料に「小麦・卵・乳」が記載されていない5製品のうち、3製品から小麦、1製品から卵白アルブミン(卵由来のたんぱく質)が検出されました。
しかも一部製品では検査キットの検出上限(20ppm)を超えていたため、正確な混入量すら不明という状況でした。
さらに驚くべきことに、日本ではヒト食品と違い、ドッグフードにアレルゲンの表示義務がないのです。
たとえ混入していたとしても、法的に問題はないというのが今の現実です。
また老犬用の療法食であっても、製造ラインの洗浄不備や管理体制の違いによって、思わぬ混入が起きている可能性も否定できません。
つまり、ドックフードのパッケージに「小麦不使用」と書かれていても、それを100%保証することは難しいのです。
知っておきたいドッグフードのアレルゲン表記のガイドライン
|
対象成分・栄養素 |
使用できる表現 |
NGとなる表現 |
備考・条件 |
|
たんぱく源(鶏・牛・卵・魚など) |
「●●を使用」「●●を含まない」 |
「●●アレルギーを抑える」「●●に効く」 |
新奇タンパクや除去食と明示した場合のみ「配慮」として認められる |
|
乳製品 |
「乳不使用」「乳製品不含有」 |
「乳アレルギーに対応」「乳アレルギーを防ぐ」 |
症状改善目的の表現は禁止。成分の有無のみを明記する |
|
穀物(小麦・とうもろこし・米など) |
「グレインフリー」「小麦不使用」 |
「グルテン過敏を改善」「腸を整える」 |
物理的に不含であることが確認されている場合のみ |
|
脂質(魚油・亜麻仁油など) |
「オメガ3を含む」「皮膚の健康をサポート」 |
「肌荒れが治る」「皮膚炎を防ぐ」 |
栄養機能としての明示は可。疾患改善表現は不可 |
|
食物繊維(野菜・ビートパルプ・玄米など) |
「腸内環境の健康維持」「毛玉の排出を助ける」 |
「便秘解消」「排便を改善する」 |
“助ける”や“サポート”などの穏やかな表現のみ可 |
(ドッグフードの表記に関する医薬品的表示ガイドラインまとめ)
「アレルギー対応フード」と書かれていると、「これなら安心」「うちの子の症状も良くなるかも」と思ってしまう方は少なくありません。
ですが、ドッグフードも人間の食品と同じく「アレルギーを治す」などの効能を明確にうたうことは法律で禁じられています。
たとえば「鶏肉不使用」「小麦を含まない」という表示は事実に基づいていれば問題ありませんが、「アレルギーを抑える」「皮膚トラブルに効く」といった表現はNG。
これは薬機法や農林水産省のガイドラインで定められており、ドッグフードはあくまで“治療ではなく健康維持”のための食品という立場にあるためです。
しかし、それでも現場では“誤解を招く言い回し”が使われているケースがあるのも事実です。
さらに、2021年に行われた調査では、表示上「不使用」とされていた療法食の一部から実際には小麦や卵といったアレルゲンが検出されたという報告もあります。
つまり、「含まれていない」と書いてあっても、製造ラインの共用や洗浄不足などにより、実際には微量の混入がある可能性があるのです。
人間向けの食品と違い、ペットフードにはアレルゲン表示の義務や基準がないという制度的な甘さも背景にあります。
だからこそ、表記だけで判断するのではなく、そのフードを作っている企業がどんな姿勢で、どんな想いで商品開発に取り組んでいるのかを見極める視点が大切です。
飼い主ができる“見えない安全”の見抜き方。それは、ラベルの裏にある「つくり手の誠実さ」に目を向けることから始まります。
出典:農林水産省「ペットフード、サプリメントにおける医薬品的表示の考え方」
犬のアレルギー対策に、本当に選ぶべきドッグフードとは?
|
選び方の観点 |
ポイント内容 |
|
① タンパク源が「単一」 |
アレルゲンの特定や管理がしやすく、除去食として使いやすい |
|
② アレルゲンとなりやすい素材を使っていない |
鶏・牛・乳製品・小麦などを避けたレシピが安心 |
|
③ 原材料がシンプル |
混入や隠れアレルゲンのリスクを減らすためにも、素材は少ないほど良い |
|
④ 添加物が少ない |
香料・着色料・保存料など、不要な添加物は皮膚炎や下痢の原因になり得る |
|
⑤ 製造元の「管理体制」や「製造環境」も確認 |
製造ラインの分離や表示制度の厳格さが、信頼できるフード選びのカギ |
(食物アレルギー対応フードのチェックポイント)
「アレルギー対応」と書いてあれば、どれも安心——そんな思い込みは、今こそ見直すべきです。
実際に獣医師たちが推奨する対策の一つは、「単一タンパク」×「低アレルゲン」素材のフード選びです。とくに鹿肉や馬肉、白身魚など、日常的に食べる機会が少ない食材を主原料にしたものは、アレルギーを起こしにくいとされています。
一方で、見た目を良くするための香料や着色料、保存期間を延ばす添加物などは、犬の体には不要どころか、かえって皮膚や腸に悪影響を及ぼす可能性もあります。
このようにアレルギー対策としてのドッグフードは、ただラベルを見るだけでは不十分です。
「成分の中身」「表示の根拠」「企業の姿勢」すべてを含めて、ようやく“選ぶ”という判断ができるのです。
次は「今与えているフード、本当にうちの子に合ってる?」と感じたときの見直しポイントを整理してみましょう。
ドッグフードの見直しポイントとは?どんな時にドッグフードを見直せば良い?
|
見直しのきっかけ |
理由 |
見分け方 |
注目すべきポイント |
|
かゆみ・赤みが続く |
アレルゲンによる慢性的な皮膚刺激が疑われる |
耳・口・指間・背中など特定部位に集中 |
原材料にアレルゲンとなるタンパクが含まれていないか確認 |
|
下痢・嘔吐が頻発 |
消化不良または不耐性・アレルギーの可能性 |
食後30分〜2時間以内の症状発生 |
穀物・添加物・乳製品などの含有チェック |
|
被毛のパサつき・毛艶の低下 |
栄養バランスの偏りや酸化した油分の摂取 |
ブラッシングでフケが増えたり抜け毛が多い |
脂肪酸やビタミンの配合・保存方法の明記 |
|
体臭や口臭が強くなった |
腸内環境や口腔内の炎症が関与 |
口の中を触ると痛がる、便臭の変化 |
プロバイオティクスや無添加処方の有無 |
|
新しいおやつやトッピング後の変化 |
軽視されがちだが、急な摂取物変更が影響 |
直近の食事履歴をチェックし反応との相関を探る |
日記形式で食事・体調の変化を記録 |
(見直しのサイン・理由・見分け方・注目ポイント)
ドッグフードの見直しが必要かどうか、それを判断するのは「症状」ではなく「変化」に気づけるかどうかにかかっています。
犬のアレルギーは、一見すると季節性の皮膚トラブルや体質の変化と区別がつきにくいため、「この子、少し歳かな」「季節の変わり目だから」と見過ごされがちです。
しかし、ずっと同じフードなのに急に涙やけが悪化した”“定期的に軟便になる”といったサイクルがある場合、それはフードに起因するアレルゲン蓄積の可能性も否定できません。
実は、こうした慢性的な不調の陰にあるのが「フード自体の品質変動」や「原材料の切り替え」であることも。
メーカーが公表しないレベルで、仕入れ先の変更や製造ロットの切り替えによって、成分が微妙に変化することは珍しくないのです。
また、市販フードの中には「グルテンフリー」と記載されていても、同じ工場で小麦入りの製品を製造しているケースもあるため、“完全にグルテンフリーかどうか”は表示だけではわかりません。
このようにドッグフードを見直すべきタイミングは、必ずしも“大きな症状が出たとき”とは限りません。
むしろ、「何となく毛艶が悪い」「最近よく耳を掻く」——このレベルでこそ、早めに切り替えを検討する価値があるのです。
さらに最近では、無添加・単一たんぱく・動物性油脂不使用など、特定ニーズに応えるフードも増えてきました。
これらのフードを選ぶときは、「なぜこの原料が使われているのか?」という理由まで知っておくことが大切です。
愛犬の食べ物アレルギー対策で意識して接種したいドッグフードの原料
知っておきたい5つの注目ポイント
-
アレルゲンになりにくい「鹿肉」や「馬肉」が推奨されている
-
グルテンを含まない「グルテンフリー」や「玄米主体」のフードが支持されている
-
食物繊維やビタミンが豊富な「野菜・雑穀」が消化と免疫維持をサポートする
-
オメガ3脂肪酸を含む「魚油」や「亜麻仁」は皮膚トラブル軽減に役立つ
-
化学添加物や保存料を避ける「無添加」処方がアレルギー予防の基本とされる
愛犬のアレルギー対策を考えている方の中には、「どんなフードが安全なのか分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
初めて選ぶときは、パッケージの言葉だけでは判断がつかず、不安になって当然です。
特に最近は“グルテンフリー”や“低アレルゲン”といった表示も増えており、何を信じていいのか迷ってしまうことでしょう。
食物アレルギー対策としては、まず鹿肉・馬肉・魚などの「新奇タンパク」や、玄米・ひよこ豆といった消化にやさしい穀類や野菜素材に注目することが重要です。
これらは犬にとって馴染みが少なく、免疫が過剰に反応しにくいとされており、実際に獣医師の間でもアレルゲン除去食として推奨されています。
また、皮膚や消化器官のトラブルを減らすには、「保存料・香料・着色料」を使っていない無添加フードを選ぶことも基本です。
そして、意外に思えるかもしれませんが、鹿肉は「低アレルゲン」だけでなく、「栄養バランスの良さ」でも高く評価されている犬に優しいタンパク源なんです。
実は犬の食物アレルギー対策になる!? 鹿肉配合のドッグフードの期待できる効果
|
観点 |
内容 |
解説 |
|
① アレルギー対策 |
鹿肉は“新奇タンパク”としてアレルギーの原因になりにくい |
鶏・牛・豚などに比べ、摂取経験が少ないためアレルゲンになりにくいとされています |
|
② 消化性の高さ |
消化吸収に優れ、胃腸トラブルを起こしにくい |
食物アレルギーの犬にとって腸内環境の安定は重要なポイントです |
|
③ 高タンパク・低脂肪 |
ダイエット中の犬にも適し、筋肉維持にも効果的 |
100g中21.8gのタンパク質を含み、脂質・カロリーが牛肉より低め |
|
④ オメガ3脂肪酸が豊富 |
慢性炎症(皮膚炎など)の抑制が期待できる |
オメガ3は皮膚や被毛の健康維持にも寄与します |
|
⑤ B群ビタミンとミネラル |
皮膚・免疫・代謝をトータルでサポート |
ビタミンB6・ナイアシン・鉄・亜鉛・セレンなどをバランス良く含有 |
(ドックフードで鹿肉が注目される5つの理由)
鹿肉を使ったドッグフードは、食物アレルギー対策の新たな選択肢として、近年注目が高まっているタンパク源です。
とくに鶏肉や牛肉にアレルギーを持つ犬にとっては、「新奇タンパク」として取り入れやすく、実際に獣医師の現場でも除去食のベースとして活用されています。
さらに、鹿肉は高タンパク・低脂肪で、100gあたりのタンパク質量が約21.8gと非常に優秀です。
一方で脂質やカロリーは鶏や牛よりも控えめなため、肥満傾向の犬や消化器が弱い犬にも向いています。
また、鹿肉はオメガ3脂肪酸を多く含み、これは皮膚のバリア機能を整えたり、慢性炎症を抑える働きが期待されます。
実際、鹿肉ベースのフードに切り替えたことで「皮膚の赤みが改善した」「かゆみが軽減した」といった飼い主の声も多く寄せられています。
加えて、鹿肉には鉄・亜鉛・ビタミンB群などのミネラル類がバランス良く含まれており、皮膚や被毛の健康だけでなく、免疫力の維持やエネルギー代謝にも効果が期待できます。
ただし注意点として、「鹿肉入り」と書かれていても、他の動物性タンパクが混ざっていたり、添加物が含まれているケースも少なくありません。
とくにアレルギー体質の犬には、“単一タンパク・無添加・製造工程の明示”といった基準で慎重に選ぶことが大切です。
出典:「This Meat Could Solve Your Pet'sWoes」
愛犬の食物アレルギー対策に、鹿肉を使ったドッグフードを試してみませんか?
この記事では、犬の食物アレルギーについて、原因や見極め方から安全なドッグフードの選び方までを、実例と研究データを交えながら丁寧にご紹介してきました。
特に注目したいのは、“見えないアレルゲン”の混入リスクと、表示だけでは分からない製造の実態です。
「低アレルゲン」と書かれていても、体に合わないケースがあること。だからこそ「何が入っているか」ではなく「どう作られているか」まで確認する姿勢が必要なのです。
そんな中でおすすめしたいのが、鹿肉を主原料にした「メゾン・ド・ジビエ」のドッグフードです。
国産の天然鹿を使用し、製造ラインもアレルゲン管理を徹底。化学添加物不使用で、単一タンパク・無添加・低脂肪という理想的なレシピが実現されています。
「うちの子、また掻いてる…」そんな日常の不安を、“食事”から見直してみませんか?
まずは、どんな原材料で、どんな想いで作られているのか、ぜひ公式ページでご確認ください。